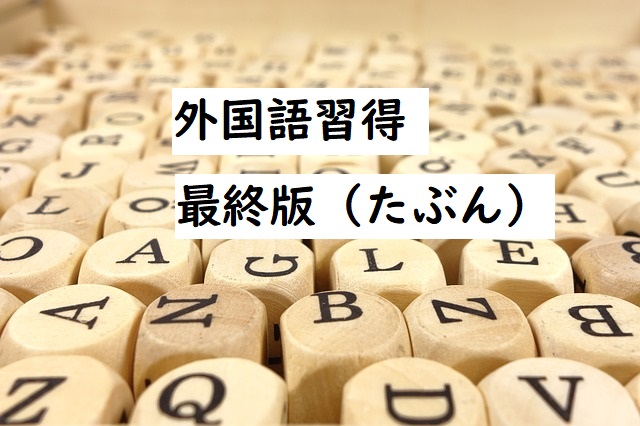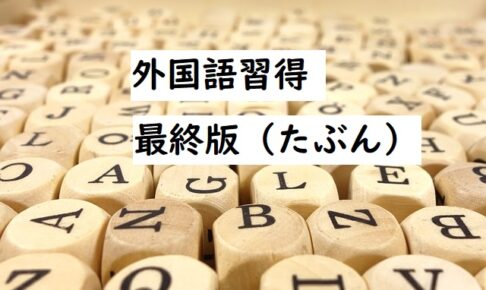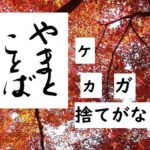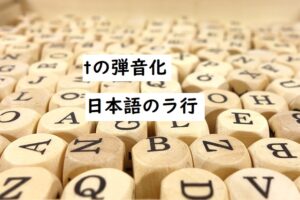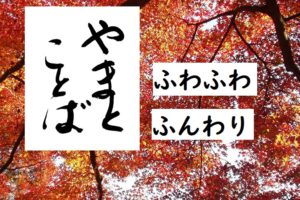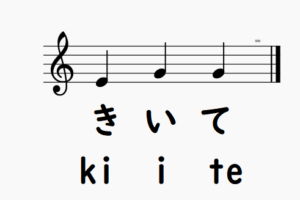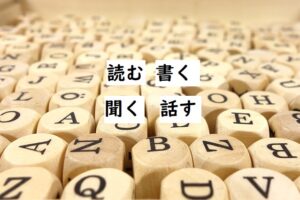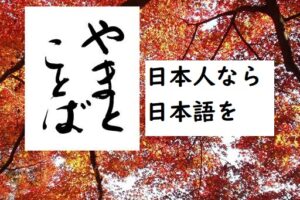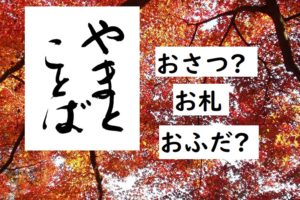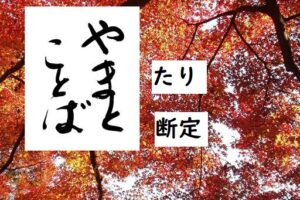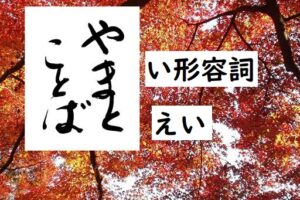目次をご覧になりたい方はクリックしてください→
「外国語」「習得」「順序」「運動」
何度もおなじような記事を書いているが、また焼き直し。
自分なりにまとめたつもり。
そろそろ打ち止めにしよう。
大前提
- あなたは赤ん坊ではない。
- 聞き流すのは風や虫の声を聞いているのとおなじ。
何万回聞いても聞き取れるようにはならない。その理由は3番。 - 知らない言葉は聞き取れないし、話せない。
とくに3番が重要。
語彙を増やすのが不可欠だが、与えられた単語帳などは何万回見ても覚えない。すぐ忘れる。
それでは行きましょうか。
外国語の勉強の順序
日本人が英語その他の外国語を勉強するときも、外国人が日本語を勉強するときもまったくおなじこと。
赤ん坊に倣うが、大人は赤ん坊ではない!
基本的には赤ん坊が母語を覚えていくのを真似すればいいのだが、あなたは赤ん坊ではない。
そしてすでに自分の母語を持ってしまっているので、赤ん坊とまったくおなじ順序とやりかたでは外国語を習得できない。
視覚がいちばん
赤ん坊はまず耳から言語を習得し、文字はあとになる。
しかしあなたは赤ん坊ではないので、文字から始めるべし。
その理由は、人は視覚からの情報がいちばん早く正確で記憶に残りやすいからだ。
耳で聞いただけのことを記憶するのはかなりむずかしい。
伝言ゲームがいい例だ。
百聞は一見にしかず
架空の怪獣の話を聞くとしよう🐉
ヘビみたいな形をしていて、鱗があって、でも足がついてて、羽もついてる。
前足には3本指があって長い爪が生えてる。
色は緑色で…
なんて話を延々と聞かされても、いざ実物を見たら自分が想像してたのとぜんぜんちがう姿と色であることはまちがいない。
音声入力、つまり耳から情報を入れても、時間がかかるくせに正確ではない。
絵や写真を視覚、目からの情報として入れれば一瞬で正確な情報が得られる。
また記憶にも残る。
また、あなたはニュースでもいいし、本の朗読でもいいが、聞いただけで正確に一字一句まちがいなく覚えられるだろうか?
無理だね。
これが文字に書いてあって、自分のペースで読む (見る) ことができて、わからない文字や単語は調べることができれば、より正確な情報を短時間で覚えられる。
また音声は自分の聞き取りと脳の処理速度におかまいなしにノンストップでどんどん進んでしまう。
インターネットの配信動画なら聞き取れなかったときは止めたり、巻き戻したりできるがこれはとてもめんどうだし、戻しすぎて何度も必要ないところを聞くことになる。
だから動画のテロップみたいに向こうのタイミングで流れて消えていく文字は論外。
印刷物や静止している文字は自分のペースで読める (見られる) 。
書く。声に出して読む。
これからの作業はとにかく書く。そして声に出して読む。
ただし正しい発音で (後述)
聞く、話すはあと。
繰り返すがあなたは赤ん坊ではない。
この順序は赤ん坊とは逆になる。
母語体系ができてしまった大人の脳にとって、
聞き取れないし、もちろん話せるわけがない
という大々前提があることを知るべし。
あなたが類稀なる聴覚の持ち主で100%音声を聞き取ったとしても、その言葉の意味を知らなければそれこそ無意味だろう😄
ピエンソケウンスウェーニョパレシードノボルベラマス
何度も書いてきたがこれは麒麟淡麗のCMでつかわれたボラーレの出だし。
これを100%聞き取れたとして、あなたは何百万回これを聞いてもけっして意味はわからないだろう。
わかるはずがない。
大人のあなたは単語の意味と文法を勉強しなければけっして外国語はわからないのだよ。
「門前の小僧習わぬ経を読む」
という諺があるが、小僧は意味のない音の羅列を暗記したにすぎない。
お経はサンスクリット語というれっきとした外国語で、ちゃんと意味のある文章である。
それを丸暗記してもそれこそ無意味なのだ。
前置きが長くなったがこれは学習に取りかかる前に知っておくべきとても大事なことだ。
文字
さあ、ここからが具体的な学習法。
文字を覚えるのは大前提。
日本人はアルファベットその他。
外国人はひらがな必須。
つぎはカタカナ。
ここまではひたすら書いて書いて丸暗記。
丸暗記と書いたが、これも五十音表をひたすら書き写すよりは、「リンゴ」のようにある長さの意味のある言葉をセットで覚えたほうが覚えやすい。
「リ」だけだと覚えられないが「リンゴ」で「リ」が思い出せなくても、わからなくても「ンゴ」が読めると「リ」が推測できる (後述)
漢字は単語の一種
漢字はぼちぼち。
漢字は意味を持つので単語とおなじ部類にはいる。
単漢字を丸暗記するな。
時間と労力の無駄だ。
漢字も単漢字ではなくセット、つまり熟語でね (後述)
次は単語
単語帳はやるな!
単語帳で片っ端に覚えるのは愚。非効率。
興味のない単語、使わない単語はいくら暗記してもすぐ忘れる。
漢字は単語・熟語として覚えるといい。
そのうえで個々の漢字のコアの意味も調べる。
たとえば「効」という漢字とコアの「効く」という意味を覚えれば、「効率」「効能」などの単語をはじめて見てもなんとなくわかるのだ。
漢字は覚えるのが大変だが、覚えるとはじめて見た知らない単語まであるていどわかってしまうという便利な道具だ。
また「効」の漢字を覚えたら「効率」「効能」など「効」がつく熟語をいくつか調べて覚える。
ぜんぶ確実に覚える必要はない。
その作業をすることで「効」の意味がより強く記憶に刻まれる。
また部首で「杉」「松」「梅」などを見たら、「木」であることはわかる。
基本語
実生活で使う基本語から覚える。
数字、日付、曜日、時間などの言いかたぐらいは最初に覚える。
じつはこれらの言葉は必須ではないというより、むしろ優先順位は低い言葉なのだが、初心者が最初にしゃべれるのは、時間や、天気や、物の値段の話だから。
これらが言えるといちおうスタート地点として外国語がしゃべれたという感覚を味わえる。
だからほどほどでいい。
レベルが上がってきたら必然的に覚えるから。
昨日何をしましたとか、今日これから何をしますとか、まして、あれがしたいとか、これがしたいとか、もし〇〇だったらなんていう仮定の文章は初心者にはむずかしいのだ。
仮定の文章が操れるようになったら、その言語をマスターしたといっても過言ではない。
名詞と動詞
名詞
人間、とくに赤ん坊は母語であっても最初は名詞 (物や人の名前) から覚える。
外国人も目で見える、手で触れる物や人の名前は視覚的にも、物理的な感覚でも一対一で理解しやすく覚えやすい。
他人がつくった既製品は覚えられない
ただよくある、リンゴ appleとか、みかん orange などという覚えかたは無駄だ。
もし自分がリンゴが好きならそれは覚えてもいいし、すぐ覚えて忘れない。
でも、他人から提示された単語帳や単語集の羅列は何回見てもすぐ忘れる。
自分が好きなもの・興味あることを覚える
もしやるなら自分が好きな食べもの、自分が好きな乗り物や楽器などの名前を絵や写真とともに覚える。
実物があればなお良い。
もし食べられるならリンゴを食べながらリンゴappleと言う。
ギターを弾きながらギターguitarと言う。むずかしいか。
ヘレン・ケラーが外の井戸水に手を触れてはじめて「水」という言葉を覚えたという話がある。
彼女は見ることはできないが直接触れる (ふれる) ことで覚えたといういい例だ。
絵文字
飛行機✈とか、ギター🎸とか。
絵文字は役に立つ。
動詞
つぎの段階は動詞 (動作) である。
目に見える動作。
触れる (さわれる) 動作。
身のまわりの日常的な動作。
思う、考えるのような目に見えない概念的な言葉は後回し。
言葉の4技能。
読む read。書く write。聞く listen。話す spek。
から始めようか。
じっさいに動作する
書く。声に出す。
読む read と紙に書く。
声に出して読む。
本でも辞書でもじっさいに読む動作をして、また「読む」と声に出す。
書く。声に出す。
は何度繰り返してもいい。
おなじように
書く write と紙に書いて、「書く」と言う。
歩く walk も紙に書いて読んでから、
じっさいに歩きながら「歩く」と繰り返して言う。
英語なら「w, a, l, k walk」とスペルと発音を繰り返してもいい。
セットで
名詞と動詞はセット
生活の中で「リンゴ」だけ単独で言うことはない。
「リンゴを食べる」のように名詞と動詞のセットで言うことが圧倒的に多い。
もちろん「食べる」だけ言うこともない。
「リンゴを食べる」「ご飯を食べる」というように名詞と動詞はいつもセットだ。
たとえば名詞のリンゴを覚えるときは、リンゴ、リンゴ、リンゴと連呼するのではなく、
「リンゴを食べる」
「リンゴを買う」
「リンゴを切る」
というようにリンゴといっしょにつかう動詞をセットで覚える。
すると、いっしょにつかう動詞はもちろん連想して覚えやすいし、意外にもその種類が少ないことに気づくだろう。
「リンゴを聞く」とか
「リンゴを読む」とか
「リンゴを運転する」とか
けっして言わないのだ。
これは母語話者が母語を話すときにもとても重要なことだ。
相手が「リンゴ」といった時点でつぎに出てくる動詞の範囲はものすごく限定されるから予測できるのだ。
何万とある単語集や辞書から引っ張り出してくる必要はない。
「お腹が…」と聞いたらあなたはそのあとに何が来ると想像するだろうか。
90%は「空いた」だろう。
お昼や夕方なら100%だろう。
ほかには「痛い」があるが、この場合相手はお腹に手を当てて顔をしかめているにちがいない。
お腹が飛ぶとか、お腹が緑とか、ぜったい言わないのだ。
動詞を覚えるときもおなじ。
「読む」を覚えるのなら
「本を読む」
「マンガを読む」
「教科書を読む」
のように「読む」といっしょにつかう名詞を覚える。
これまたいっしょにつかう名詞がとても少ないことに気づくだろう。
「行間を読む」なんてのは上級レベルなので初心者は覚えなくていい。
「教科書」だけではむずかしい漢字のむずかしい単語だが、「教科書を読む」というセットだと、「教科書」は「読む」対象で、文字が並んでいる書物の一種だということは容易に想像がつく。
さらに「教」という漢字が「おしえる teach」の意味だということを知っていれば、はじめて見た単語でも「これはtextbookのことではないか?」と推測することさえできてしまう。
このように名詞と動詞はいつも仲良しなのでセットで覚える。
形容詞・副詞は最後
形容詞や副詞は言葉の補足説明のためのおまけ、オプションであって必須ではない。
たとえば「リンゴを食べる」というとき、色が「赤い」か「青い」かは必須ではないのだ。
たとえば「走る」というとき、「速く」か「ゆっくり」かは必須ではないのだ。
「リンゴを食べる」が当たりまえのように言えるようになったら、はじめて
「赤いリンゴを食べる」
「青いリンゴを食べる」
のように形容詞をつければいい。
これもリンゴなら、白や黒はないわけだ。
かなり範囲が絞られる。
「走る」につく形容詞の連用形や副詞も「速く」「ゆっくり」はあるけど、「おいしく」はぜったいない。
これらの言葉もつかう相手は限られていて、何万語の中からさがす必要はないのだ。
フレーズ
こうして名詞+動詞に形容詞や副詞のおまけがつけられるようになったら、今までとおなじように単語レベルではなくあるていどの長さでまとまったフレーズで覚える。
経験を表す「~たことがある」を
「た+こと+が+ある」に分解して文法的意味を考えるのではなく「~たことがある」で覚えてしまおう。
なぜなら、このバリエーションはほぼないといっていいからだ。
この形でしかつかわない。
「ある」が「あります」になるくらいで、「あらない」とか「あれ」とか「あろう」のように活用はしないのだ。
「行ったことがある」
「見たことがある」
「聞いたことがある」
「食べたことがある」
会話でとてもよくつかう。
英語なら「have done」
「have been to」
「have seen」
「have heard」
「have eaten」
いちいちhave+過去分詞と考えるのではなく、「have+seen」という形で覚えてしまう。
I have seen the movie. その映画を見たことがある。
I have seen the picture. その絵を見たことがある。
のように例文で覚えておけば、seenの後ろの名詞だけ入れ替えればいいのでかんたんだ。
リスニングとスピーキング
大人はこれが最後だ。
何度も繰り返すが
知らない言葉は聞き取れないし、話せない
漫然と外国語のドラマを見ていても言葉は覚えられない。
聞き流すだけなんて論外。
まず自分で単語とフレーズを毎日蓄積していって、そのうえではじめて聞き取れるようになる。
聞き流すな。全身全霊で聞け。全身を使え。
そのために単語を覚えるときは書くのと声を出して読むことが大事だ。
視覚と手の運動神経、そして口・舌・喉の運動神経と聴覚すべてを連携させる。
アホな政治家の一つ覚えを借りれば、すべての感覚神経と運動神経を緊密に連携させるのだ😄
母語体系ができあがった大人は母語 (日本人なら日本語) 以外の音は雑音・背景音としてフィルターにかけ遮断してしまう。
外国語をただ聞き流していれば、それこそ風や虫の声とおなじようにフィルターにかけられ脳はその音を聞かない。
この機能がなければまわりがうるさくて人の声が聞き取れないからだ。
外国語の音を言語として脳が処理するには、その音に慣れる必要もあるがいちばん重要なのはその音と意味を知っていることである。
卑近な例を持ち出せば、おじさんはイタリア語のポッドキャストを聞いたとき「カルボナーラ」だけははっきり聞こえたのだ😄
それはその単語の音と意味を知っていたからに他ならない。
もちろんそれ以外の知らないイタリア語はいっさい聞き取れないし、意味もわからない。
正しい発音で読む
何度も言うが、あなたは赤ん坊ではない。
母語の文法と発音体系に汚れてしまっている。
残念ながら赤ん坊とちがってあなたは無垢ではないのだ。
漫然と読んでいると母語の発音になってしまう。
たとえばresultを「リザルト」とカタカナで覚えてカタカナで読んでいると、せっかく覚えたつもりでもじっさいの音は「リゾート」に近いので聞き取れないのだ。
「リザルト」と「リゾート」ではまったくちがう音だ。
これは「リゾート」で覚えて「リゾート」と発音する。
もちろん「リゾート」でもない。
ただしresortでもないのだよ。
また英語のpodcastで「メラゴー」というのが何度も聞こえて、どうしてもわからないので文字のスクリプトを読んだらmarigold (マリーゴールド) だったことがある。
マリーゴールドでいくら覚えてもけっして聞き取ることはできない。
国際音声記号と音声学と口腔断面図
あなたが英語その他外国語を勉強するのならカタカナから完全に離脱してIPA (国際音声記号) と音声学と口腔断面図を勉強すること。
カタカナよ、さよなら👋
IPAの発音で覚えなければ何万時間、何万回発音練習やリスニングをしても聞き取れるようにならないし、話せるようにならない。
まちがった発音をいくら練習して覚えても聞き取れるわけがない。
カタカナは忘れろ。
このへんのことは他の記事に書いてあるので参照されたし。
外国人が日本語を勉強するのなら、アルファベットは忘れてひらがな・カタカナ・漢字で覚えろ。
おじさんがもしアラビア語を勉強するのならぜったいアラビア文字を勉強する。
まちがいない。
自分で興味があることを自分で調べる→忘れない
他人がつくった単語集やフレーズ集はやるな
自分で調べて勉強して作り上げたものはOK。
卑近な例を出そう。
あなたは友だちの車の助手席に乗ってどこかへ出かける。
運転手にお任せだ。
あなたは景色を見ている。 (はずだ)
ところが後日、それとおなじ道を走っておなじところに行こうとしたら迷子になってしまった。
人から見せられたものをただ漫然と見ていても覚えないということだ。
これはかりに道を覚えようとしていても、助手席や後部座席に座っているとなかなか覚えられない。
とうぜんナビを使ったら覚えない。
もちろん道を覚える必要がなければ大いに使え。
おじさんも使っている😄
自分で調べろ
行きたいところがある。
自分で地図で調べる。
どの道がいいかいくつか吟味する。
できればラリーのコマ図のように交差点と目印とだいたいの区間距離・所要時間まで書くとかなり覚える。
外国語を覚えるのといっしょ。
見ただけは忘れる。
地図を見ただけではダメ。
かんたんな記号でもいいから書く。
辞書や教科書を見ただけではダメ。
助手席で景色を眺めているのとおなじ。
すぐ忘れる。
自分で運転しろ。運動神経を使え!
自分で運転する意味は運動神経と連携することだ。
じっさいに交差点の手前で左に曲がるぞ、と意識してウィンカーを出して、前後左右の安全確認をしてハンドルを動かす。
この観察したり、考えたり、記憶したりすることと、動作が結びついて同時に起こることで記憶はさらに脳に強く刻み込まれ、定着するのだ。
機械の操作なんかもそうね。
先輩がこれこれ、このボタンを押してから、つぎはこのレバーを引いてと、ぜんぶやってしまうと覚えられない。
おじさんは後輩に教えるときにはかならず、後輩にやらせる。
このボタンを押してと言っても心を鬼にして自分では押さない。
後輩に押させる。
手を動かすのがめんどうだから?😄
いえいえ、じっさいに自分の指でボタンを押したほうが忘れないからだ。
フィードバックが記憶を定着させる
機械のボタンを押したり、ハンドルを切ったりするということは、まずその操作を記憶から引っ張り出し、手の運動神経に司令を出し、手がその場所まで行くのを目 (視覚) その他の感覚器官で追って、いま手がどのへんまで行ったかフィードバックして、そろそろ動きを止めろとか、もうすこし左上へとかずっと脳と手の運動神経でやり取りしているわけだ。
そしてボタンを押したらその感触が脳に伝わる。
むかしのロボットはボタンを押しつぶしてしまった。
触った感覚がなかったからだ。
今は人間とおなじようにどれぐらいの圧力がかかっているかフィードバックする。
人間は指先の圧力を神経で脳に伝えて、脳はそろそろ力を緩めてもいいぞと指令を出す。
短い間にこういうやり取りをすることで記憶はとても強固に定着するのだ。
見ているだけじゃダメな理由はわかったかな。
見ているだけは景色を眺めているのとおなじ。
目からはいった光は視神経を通って脳に伝わり、脳はそのイメージを確認しただけで作業を終えてしまう。
そこに木が何本生えてたか、ビルの窓はいくつあったか正確な数は覚えていないのだよ。
もしそこでスケッチをすれば、木が何本で、枝はどんな感じか、葉っぱの形は?ビルの窓は縦何枚、横何枚まで数えて手を動かさないと書けない。
ここでもフィードバックが必要で、手を動かしながら目でその動きを見て、脳にフィードバックを送り、脳はもうちょっと右に伸ばしてとか、そろそろ手を止めろと司令を出すわけだ。
こうして絵を書いたら、しばらくは窓の数を覚えているにちがいない。
むすび
とにかく書く。声を出して読む。
体中の感覚神経と運動神経をつかって記憶の網を張る。
単独の記憶はすぐ消えてしまうがいろんなものと結びついた記憶は残る。
バラバラの文字ではなく意味のある文字列、つまり単語単位で文字を覚える。
絵や写真、実物があれば尚可。
単漢字ではなく熟語。
単語ではなく、名詞と動詞セット。
さらにフレーズ、お決まりの表現の雛形を覚える。
座ってただ文字を眺めるのではなく、関連した動作をする。
他人がつくった教材は単語集・フレーズ集ふくめてダメ。
自分が興味あることを自分で調べて蓄積していく。
自分で調べて自分で運転しないと道は覚えない。