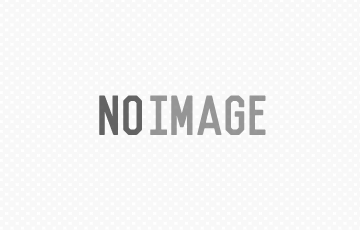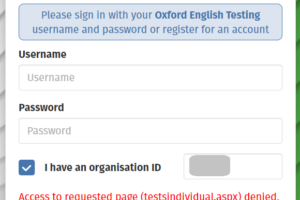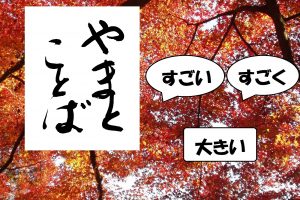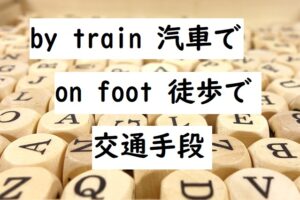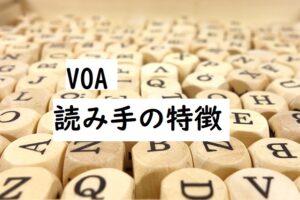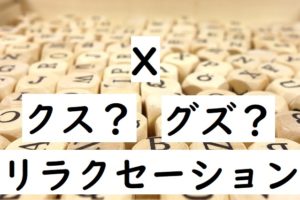目次をご覧になりたい方はクリックしてください→
「スピーキング」「外国語」
話す前に作文しなければならない
アウトプットは大事だけど、アウトプットするためにはその前に大量のインプットが必要です。
自分の中に何もないのにアウトプットはできません。
母語では頭に浮かんだ単語を思い浮かんだ順番にダラダラと口から出すだけで文章になります。
あとは無意識に習得した文法と言われるものにしたがって形を変えたり助詞をつけたりすれば母語になります。
だからじっさいの会話では文法的におかしかったり、言い直しや、付け足しなどが起こります。
「私の趣味は、お酒を飲みながら寝転がって音楽を聞くことが好きです」なんていう文章も出てきますが会話ではOKです。
文法的には「私の趣味は〇〇です」か「私は〇〇が好きです」が正しくて、「趣味」と「好き」は重複してるんだけどこういうことが起こります。
英作文
すべての外国語がそうですが代表として英語にしておきましょう。
外国人が日本語を勉強する場合もまったくおなじです。
母語とちがい母語体系ができあがりそれにどっぷり浸かった大人は、外国の映画を見てるだけでスラスラと外国語がしゃべれるようにはなりません。
よく「わたしは教科書をつかったり文法を勉強したりしません」という人がいます。
たしかにそれにしてはよくできてるけど、こういう人たちはまちがいが定着していて、いつもまちがった言い方をして気づきもしません。
意味はわかるけど、これは外国語をマスターしたとは言いません。
もちろん本人が話が通じればそれでいいと言うならそれでかまいません。
口から文章を吐き出すには、頭で作文しなければならない
母語話者とちがうのは、頭に浮かんだ単語を羅列しただけではちゃんとした文章にはならないということです。
とくにSVOの言語とSOVの言語では顕著です。
「わたし 行く 学校」でもわかるけど、わかるというだけです。
頭の中で作文するのはかなり大変です。
とうぜんふだんの練習としては紙に向かってたくさん作文することです。
ただ書き写すのではなく、自分で文章を考えて書くのです。
場面を想像して文章を書く
教科書やネットに書いてある文章をただ覚えようとしても頭にはいりません。
すぐ忘れます。
自分が自分の国で母国語でやっている会話を想像して、それを外国語に翻訳します。
日常生活でもいいし、海外旅行したときに空港やホテルであるだろう会話。
または彼女を食事に誘うときの文言でもいいです😄
これをなめてはいけません。
動機が不純、もとい強ければ強いほど語学にかぎらず習い事は上達するものです。
翻訳アプリは参考にしてもいいけどまず自分で考えましょう。
手で書いて、それから声に出します。
これを始めるとすぐわかることがあります。
自分の語彙がいかに少ないか
語彙
日本語の文章を考えてそれを英訳する。
それから確認のために翻訳アプリを使う。
おすすめはdeepLです。
google翻訳は精度が低いです。
deepLも完璧ではないので、その翻訳をもとにまた自分で辞書を引いて確認します。
人間もおなじだけど、単語レベルだと精度はかなり低くなります。
たとえばtakeだけだと、それに相当する日本語がたくさん出てきます。
あるていどの長さを持った文章にしないと、それに合った訳語は出てきません。
英作文をしていると、文法以前に「これは英語では何て言うの?」ということがそのつど出てきます。
調べます。
こうやって調べた英単語は忘れません。
また単語レベルではなく文章・フレーズとして覚えると忘れません。
暗記アプリなどをつかって興味のない単語を機械的に覚えるのはやめましょう。
何度やっても覚えないから。
使わない言葉はすぐ忘れてしまいます。
文法・言い回し
それから単語はわかるんだけど、どんなふうに言ったら自分の言いたいことが伝えられるかわからないということもたくさん出てきます。
外国語でむずかしいのは仮定法ですね。
「明日雨が降ったら、運動会は中止です」というような文章です。
このへんは単語を調べるだけでは無理で、文法を勉強する必要が出てきます。
文法と考えると抵抗があれば、言い回し・言いかたと考えればいいでしょう。
これも1つの決まったフレーズを覚えれば、あとはその中の単語を入れ替えるだけで文章ができます。
発音
これは言わずもがな。
だれもがこのことはわかっていると思うので多くは書きません。
また多くの人はこのことばかり気にしていて、じつは大事なことは「語彙」と「フレーズ」だということがわかっていません。
話すためにはたくさんの部品 (語彙) と決まったパターン (フレーズ) を自分の引き出しに入れておくインプットが必要です。
とにかく声に出して読む
わざわざ本を買わなくてもいいです。
ネットには文字があふれているので、自分が興味のある文章を声に出して読みます。
じっさいに口を動かさないとダメです。
カタカナ語は忘れろ
外国語をカタカナで書いて、それを日本語の発音で読む。
論外です。
その国の文字で読みます。
ディズニーランドとカタカナで読めば、「でぃずにーらんど」という日本語の発音になってしまいます。
かならずDisneylandとアルファベットで読んで覚えます。
また日本にはインチキカタカナ語が氾濫しています。
例:
キャリア→カリア
カジュアル→キャジュアル
オーブン→アヴン
またallはオール、callはコールと発音するように、「オール」です。
したがってnaturalはナチュラルではなく「ナチュロー (ル) 」です。
だからカタカナ語は忘れてくださいね😄
国際音声記号と口腔断面図
ネイティブの発音に近づけるには聞いただけではダメです。
これらを勉強しましょう。
聞いただけではどうしても母語の発音になってしまうからです。
とくに r の音は特殊で、日本語は「弾き音」、英語は「接近音」なのでまったくちがう音です。
これはどうやってその音を出しているかを理論的に物理的に理解しないかぎり、100年リスニングとスピーキングを練習しても獲得できません。
f は下の歯で上唇を噛む。
th は上の歯で舌を噛む。
このへんは学校で教えてくれるんだけど、とにかく r に関しては無法地帯、野放しの状態です。
先生も知らないんじゃないでしょうか。
日本語風の r の発音は100年やっても無駄、無意味です。
理論的に理解して、テニスやスキーの練習をするのとおなじように舌の訓練が必要です。
見ただけ聞いただけでは習得できない
よくある悪いコーチ。
「わたしがやるのを真似してくださいね」
テニスやスキーのコーチ。
いえいえ、見て真似するだけで上達するならコーチ・先生は要りません。
語学もおなじでネイティブの発音を聞いて真似するだけでは習得できないんですよ。
自分ではそれに似せてるつもりでも自己流の癖 (母語体系) が染み付いています。
自分では真似してるつもりでも、母語の似た音で代用してるだけです。
理論的に物理的に理解して、それに近づける訓練をしなければ。
何が母語とちがうのか、習得しようとしている外国語はどのような物理で動いているのか?
スキーにたとえるなら、ただうまい人の滑り方を見て真似してもけっきょく自己流から離れられない。
具体的に、膝を曲げるとか、腰を落とすとか、前傾にならないように上体を起こすとか、そういう姿勢や筋肉の使い方を理解して訓練しなければ上達はありません。
自分とうまい人 (ネイティブ) のちがいは何かをきちんと理解することが必要です。
見ただけで100万年練習しても悪い姿勢 (発音や文法) を定着させるだけです。
とりあえずどんな斜面でも降りられるけどへっぴり腰というやつです。
それは語学でいえば、とりあえず通じるけど万年カタコトです。
むすび
スピーキングが上達するにはまず語彙とフレーズを大量に仕込むこと。
これはあるていどやったら終わりではなく、死ぬまで続けます😄
じっさいおじさんは食事中でも「これは英語で何ていうのかな?」と思うと電子辞書を引いてしまいます。
じっさいに話すことは大事だけど闇雲に読んでも正しい発音は得られない。
国際音声記号と口腔断面図を勉強して、物理的に舌をどのように動かすかを勉強してその訓練をすること。
正しい発音を訓練しなければ意味がありません。
それはテニスやスキーの練習とまったくおなじだということです。


わたしは日本語教師をしています
プロフィール・レッスン予約はこちら。
表示名はToshiです。
https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese