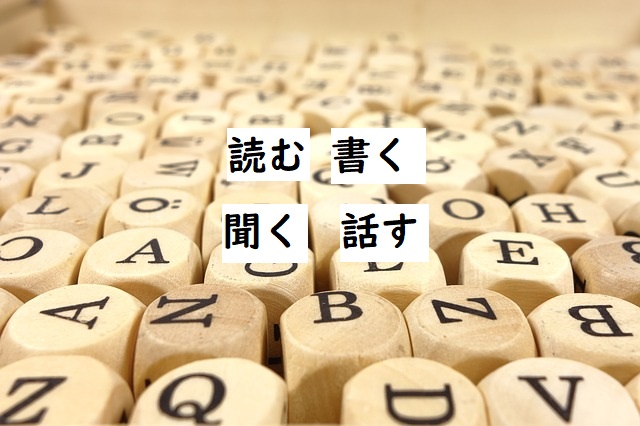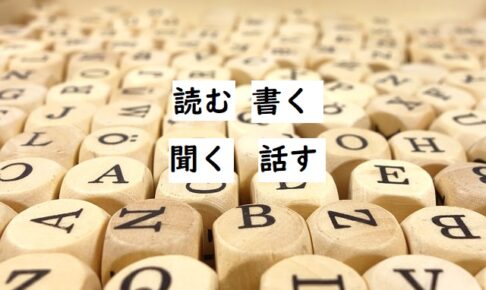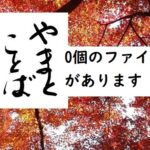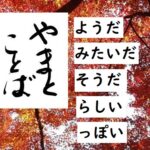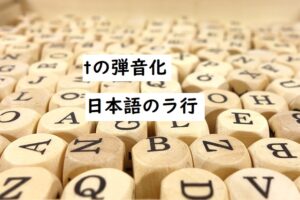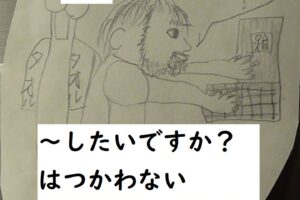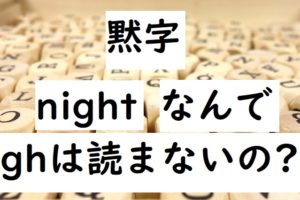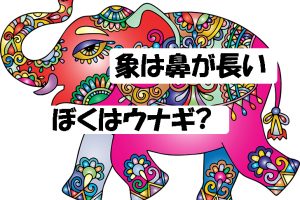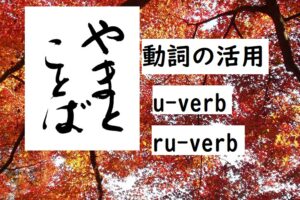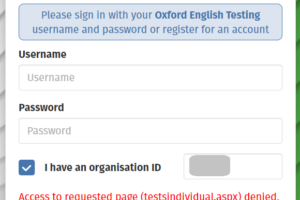目次をご覧になりたい方はクリックしてください→
「読む」「書く」「聞く」「話す」
言葉の基本技能4つ
読む、書く、聞く、話すです。
「読み書き」という言葉はあるけど、なぜか「聞き話し」という言葉はありません。
考えてみれば母語話者は「聞く」と「話す」ができるのは当たりまえで、読み書きのほうは特別な教育を受けないと獲得できません。
識字率という言葉があるくらい、日本ではほぼ100%ですが、世界には読み書きができない人はけっこういます。
それ以前に文字が存在しない世界さえあります。
日本人もえらそうなことを言ってますが5世紀ごろに中国から漢字がはいってくるまでは文字がありませんでしたから😄
日本にも文字があったという説もありますが眉唾です。
また文字がはいってきても読み書きができるのはほんの一握りの人で一般庶民はできないほうが当たりまえでした。
それで生きて行くのに何も問題ありません。
農民は作物をつくることをおぼえればいいので、相対性理論など知る必要もありませんでしたから。
寺子屋などというものが現れ、一般庶民が文字を習うようになったのは江戸時代になってからです。
母語
このように母語 (日本人なら日本語) はそれこそお母さんから、いえお父さんも兄弟もその他まわりの人もいますが、耳で聞いておぼえて、口をテキトーに動かしてみて息を吐いてみてどんな音が出るか自分の耳で聞いて、こうするとこの音が出るということを体得していきます。
第2外国語
うんざりするほど「聞き流すだけでおぼえられる」という英語教材が出回っていますが「聞いておぼえられるのは赤ん坊だけ」です。
それから赤ん坊の名誉のために言っておきますが、赤ん坊はけっして聞き流していません。
メチャクチャ大人の会話を聞いています。
それが死活問題だからです。
子は親の鏡
それから赤ん坊はメチャクチャ大人のやることを見ています。
気をつけてくださいね。
いい悪いという判断はありません。
あなたの言うこと、為すこと真似しますから。
なんでこんなこと言うんだ?こんなことするんだ?
いえいえ、それはあなたが言ったりしたりしているからに他なりません😄
外国語。聞いて覚えられるのは、赤ん坊のうちだけ! (舌の位置)
文法と語彙が必要
また話が逸れた。
大人が第2外国語としておぼえるときには文法と語彙は必須です。
これをしない人はアメリカに10年住んでいても “Where park?” くらいのことしか言えないんです。
それでも生活するだけなら問題ありません。
それより日本に何十年いるという、とくにアメリカ人を見てください。
まったく日本語がしゃべれません。
ていうかしゃべろうとする気がありません。
だってまわりの日本人が英語をしゃべってくれるから。
さすがに日本に住んでいれば在日アメリカ人としか付き合わなくても日本語の「音」にはさらされているはずです。
でも覚えないでしょ。
聞き流しているのは言語ではなくて背景雑音にすぎないからです。
文字どおり聞き流しています。
日本人が発している音は、虫の声、風の音と変わりありません😄
日本の英語教育
とかく日本の英語教育が批判されますが文法と語彙は必須です。
「でも日本人は英語がしゃべれないではないか」
当たりまえです。
しゃべる練習をしてないから。
日本の学校では読み書きの練習しかしません。
だからしゃべれるはずがありません。
でも、だからといって文法と語彙を軽んじてはいけません。
問題は「それしかしない」ことです。
本を読むだけならそれでOKです。
でももし会話をしたいのなら「聞く」「話す」の練習をしなければなりません。
あなたが何を求めるかですね。
そして、逆説的ですが「聞く」「話す」ためには文法と語彙を勉強しておぼえなければなりません。
これが大事。
教材
おじさんは主にvoaをつかっています。
アプリは全般にいえますが広告が鬱陶しいのでスマホでもふつうにサイトを見ています。
アプリを入れる必要はまったくありません。
あれは広告を入れたりお金を取るためのものです😄
家ではもちろんPCで見ています。
それからyoutubeやamazon prime videoで英語の動画を見ます。
教育なものでもいいし、娯楽映画でもまったくかまいません。
自分が興味があるもののほうが見ようとする意欲が湧くし、続けられます。
無理して教育的なものを見ようとして嫌になってしまったら本末転倒です。
4技能の練習方法
- 聞く (文字は見ない。意味より音や単語を聞き取る)
- 文字を見ながら聞く (黙読。意味を理解する)
- 書き出す (意味を調べる)
- 聞く (2回目。文字は見ない。意味を理解する)
- 読む (音読。発音練習)
- 作文
1. 聞く (聞き取りの練習)
文字は見ない。
意味より、発音と聞き取れる単語に集中する。
聞き流すな。耳をダンボにして聞け👂
赤ん坊とちがい大人は無条件ですべての音を取りこむ能力は失っています。
逆に言えば、そうでないと大人は言語を聞き取るのがむずかしくなります。
自然に言語と背景雑音をフィルターにかけて言語だけが脳に届くようになっています。
さいしょに「聞く」を持ってきたけど、これはあくまで「ある程度、その言語を文法的に勉強して単語もおぼえている」ということを前提にしています。
まったく未知の言語は聞くだけではまったく勉強になりません。
2. 聞く (黙読)
文字を見ながら聞く。
耳だけでは聞き取れなかった単語の確認と、話題は何かを見る。
宇宙についての話か?
食べものの話か?
3. 書く (意味を調べる)
知らない単語を書き出して辞書で意味を調べる。
辞書を「見るだけ」はダメ。
ノートにまとめる必要はなく、メモ用紙でもいいので「英単語」とその「日本語の意味」を紙に手で書く。
ノートに書いてもどうせあとで見ることはありません😅
それより忘れたら何度でも紙に書くほうが覚えます。
また文法的につかいかたがわからないフレーズが出てきたらそれも調べます。
あなたがまったくの初心者でほとんど単語を知らないのなら調べるのに時間がかかるでしょう。
ある程度、意味がわかる人は全部調べずに、この単語だけはまったく初めてだとか、どうやらこれがキーワードでこれがわからないとこの文章の意味がわからないというものだけ調べます。
句動詞 (フレーズ)
たとえばtakeという単語だけだと、とてつもなくたくさんの意味が出てきます。
じつは日本語でもおなじことがあるんだけど母語話者だと気づきません。
それは単語レベルで決まった意味があるわけではなく、文脈やいっしょにつかう主語や目的語、助詞などによって意味が変わります。
だから単語レベルで覚えるのはあまり意味がありません。
takeの例なら、
take place 行われる
take part in 参加する
take care 気をつける
take over 買収する、乗っ取る
overtake 追いつく、追い越す (語順がちがっても意味が変わる😮)
のように句動詞で覚えたほうがいいです。
というよりセットで覚えるべきです。
take 取る
だけ覚えてもtake part inの意味はわかりませんから😄
anki
おじさんはエクセル (オープンオフィス) のA列に英単語、B列に日本語を書いて.tsv (タブ形式) でダウンロードしてから、ankiにimportしています。
ankiは単語帳ですが、書いておきながらあまり根を詰めてやらないほうがいいです😄
単語帳というのは何の脈絡もなく断片的なので覚えにくいです。
ankiに時間をかけるなら、その時間をある長さと意味のある文章を読むのにつかったほうがいいです。
その中でわからない単語、見たことあるんだけど思い出せない単語を調べるほうが覚えやすいです。
日本語でも「肝に銘ずる」なら意味がわかるけど、じゃあ「銘ずる」って何ですか?と聞かれるとよくわからないでしょ。
これも単語レベルだといろんな意味があって覚えられない例です。
書くとおぼえる (短期記憶と運動神経とフィードバック)
字を書くためには短期的にでも記憶しなければできません。
たとえば書道で臨書といってお手本を見ながら書き写す練習がありますが、あなたは右目でお手本を見ながら同時に左目で半紙を見て書けますか?
むりですね。
ちらっとお手本を見て線の位置・太さ・曲がり具合を瞬間的に記憶して、その記憶を頼りに真っ白な半紙に目を移し、脳は運動神経を通ってあなたの手に指令を出し手を動かし、さらにあなたはそこに写し出される黒い墨の軌跡を目で追いながら、またその情報を脳に伝えて、もうすこし強く押すのか、曲げるのか、止めるのか、また脳から命令をもらいます。
これをフィードバックといいます。
見ただけだと景色を眺めているのといっしょで、あとで木は何本生えていましたか?窓の数はいくつでしたか?と聞かれてもおぼえていないでしょう。
知らない言葉は聞き取れない
知らない言葉は耳にはいりません。
上に書いたように背景雑音として処理されてしまいます。
自分の頭の中にある辞書とおなじ音がはいってきたときに、スイッチが押されて意味のある言語として処理されます。
またかりに聞き取れたとしても意味がわからなければそれこそ意味がないです。
セミの鳴き声を完璧にマスターして「ミーン、ミンミンミンミ~ン」と言っても、意味はわからないですよね😄
セミ語の「ミンミン」の意味を知る必要があります。
4. 聞く (2回目)
また文字を見ないで全力で聞きます。
今度は1回目よりいろんな単語が耳にはいってくるはずです。
それはあなたの辞書に新しい語彙が書きこまれたからです。
2回目は発音より、単語の意味と話の内容に集中します。
5. 読む (音読)
しゃべる練習をしてないのにしゃべれるわけがない。
文字を景色として眺めるのではなく、声帯と舌と唇を動かして発音します。
とくに意識するのは舌です。
声を出して読みましょう。
単語の意味より発音に集中します。
ネイティブが発音したのとおなじように発音します。
口腔断面図
外国語の発音を修得するのに口腔断面図は欠かせません。
Japanese phonetic pronunciation 音声学的な発音 ~ 日本語
これは日本語の音声ですがこれを知るだけでも外国語の発音に対する認識がかなり変わります。
国際音声記号で検索するとたくさん出てきます。
卑近な例では、日本語のラ行は弾き音で、英語のrは接近音です。
しかし、母語の発音の体系ができあがった大人には「聞くだけ」ではそのちがいはわかりません。
聞き取ることはできるかもしれないけど発音するときには母語の発音になってしまいます。
何も日本人だけの話じゃありません。
おなじ英語をしゃべっても、ドイツ人ならドイツ語、スペイン人ならスペイン語、ロシア人ならロシア語に聞こえてしまうのは、かれらが母語の発音でしゃべっているからです。
日本人は英語のraを弾き音の「ら」で発音してしまうので、英語のraは接近音で舌はどこにもつけないということをいつも意識しないと、何百万回聞き取りをして発音練習をしても日本語の「ら」になってしまいます。
正しい発音は「聞くだけ」ではけっして獲得できません。
6. 作文
さてこれも学校でやらされたいやな作業かもしれませんが、じつは「話す」ということは「作文」をするということです。
作文ができないと話せません😮
頭の中で単語を引っ張り出してきて組み立てる。
オンラインで会話練習などしてみればよくわかりますが、まず聞き取れないと文字どおり話にならない。
そしてこんどは自分が話そうとしたときに単語が出てこないとやはり話になりません。
とりあえず単語を知っていれば単語の羅列だけでもなんとか意図は伝えられる。
それだけでも上出来です。
そのつぎの段階として、正確でなくても文章として単語を組み立てる必要があります。
人間を相手に話す前に、作文をたくさんしましょう。
正しいかどうかは二の次。
単語を組み立てる練習です。
そうしないと
「ほら、あの、あれが、あれよ。ほら、わかるが?」
という日本人同士でもわからないうめき声になってしまいます😄

何を求めるか?
聞くが2回 (実質3回) ありますが、それはおじさんが個人的に「聞き取り」がいちばん苦手だからです😅
これを全部やる必要はなくて、あなたが苦手なところ、あるいは磨きたい技能を重点的にやってください。
聞き取りと話すのはぜんぜん問題ないという人は、読み書きをたくさんやるといいです。
ただし、単語もあまり知らない、文法もわかってない人が、スラスラ話せるということはありえませんが。
スピード
はじめはスピードが遅い音声を聞きましょう。
よくふつうの会話はゆっくりじゃないとか、相手はゆっくりしゃべってくれないとかいう人がいますが、これもナンセンスです。
いきなり最速の会話を何百万回聞いても、いつまで経っても永遠に聞き取れるようにはなりません。
それ以前に練習するのが嫌になってきます。
「あっ、今、単語が聞き取れた!」
「あっ、今のところ、意味がわかった!」
という小さな喜びが、練習をつづける力になります。
あなたが楽器の演奏をしている人ならわかると思いますが、はじめから速いスケールは弾けません。
はじめはゆっくり。
慣れたらすこしずつスピードを上げています。
おじさんは耳コピをすることがありますが、言語の聞き取りとまったくおなじで、通常再生ではコピーできません。
スピードを落としたり、一時停止しながら聞き取り、書き取ります。
あなたがモータースポーツをしている人なら、はじめはゆっくり走り、すこしずつスピードを上げていきます。
いきなりレコードタイムとおなじスピードで走ることはできません。
初心者がそれをやればコースアウトして壁に激突することは必至です😄
これらは耳のセンサーで検知した音を脳に伝え、脳の処理速度と運動神経の連携と上達が必要で、言葉も声帯と舌と唇を動かす運動なので、スポーツの練習となんら変わりはありません。
おじさんはvoaを聞いています。
youtubeなどを聞くのなら、「スロー再生→ふつうの速さ→加速」という手もあります。
繰りかえします。
まったく聞き取れない音声を何百万回聞いても聞き取れるようにはなりません。
あなたは赤ん坊ではないのだから。
忍者は麻の種を植える
忍者は跳躍の訓練として麻の種を植え、その上を飛び越える練習をするそうです。
しらんけど😄
はじめは平らな地面なのでカンタンです。
麻の芽が出てきて伸びはじめます。
麻の成長は早いので毎日、伸びていきます。
大事なのはいきなり2mの壁を飛び越える練習をしても飛び越えられないのでまったく練習にならないということです。
それよりハードルを少しずつ上げていくほうが練習になるんです。
気がついたら2m飛べるようになっていたということです。
おなじ文章を短い範囲で
つねに新しい音声を聞いてもなかなか耳にはいってきません。
また長い文章は疲れるし飽きてきます。
勉強も運動の練習も短い時間で集中してやったほうがいいです。
いやになるまでやらないほうがいいです。
長くても5分以内、はじめは1分くらいの文章を聞きます。
そしておなじ文章を繰りかえし聞いていると、1回目より2回目、2回目より3回目のほうが聞き取れる単語が増えてきます。
いきなり1時間練習するより、5分を12回やったほうが効果的です。
わたしは日本語教師をしています
プロフィール・レッスン予約はこちら。
表示名はToshiです。
https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese