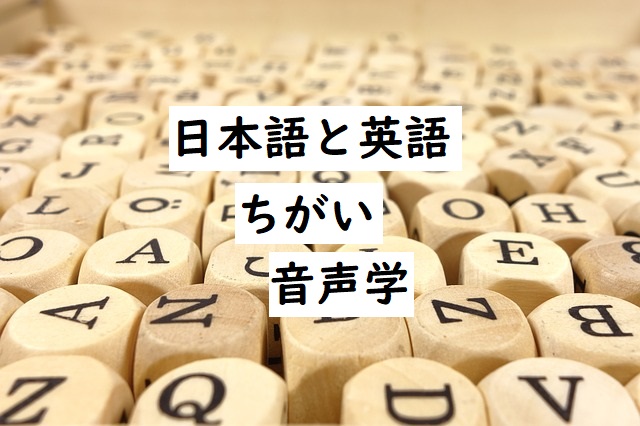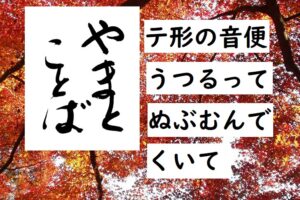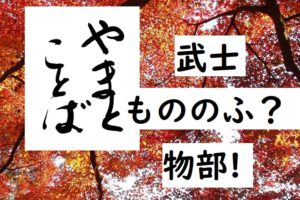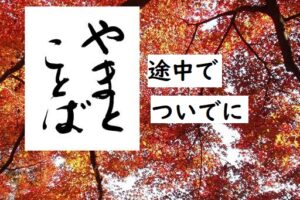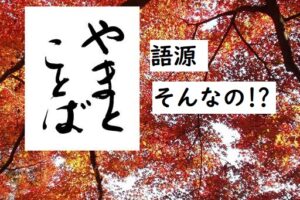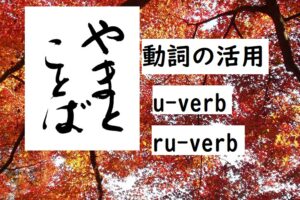目次をご覧になりたい方はクリックしてください→
「日本語」「英語」「音声学」
はじめに
英語のいちばんむずかしいところは発音です。
文法はほかのヨーロッパの言語に比べればかなりかんたんなほうです。
それは英語が、いやイギリスが様々な国や民族に次から次へと侵略され、言葉もごった煮のようになって簡略化されてしまった結果です。
混合言語の一種です。
だれが最初にいたかはわからないけど遡るとまずケルト語 (ケルト人、ケルト族) です。
それからゲルマン民族大移動でゲルマン語 (ゲルマン人) の襲来を受けます。
だからおなじゲルマン語のドイツ語にとてもよく似ています。
そしてさらにノルマン人 (バイキングの子孫でフランスに定着した民族) に侵略され、1066年のノルマン・コンクエストでフランス人 (じつはノルマン人) のギョーム2世が、ウィリアム1世としてイギリスを支配します。
ドイツ語は、というかふつうのヨーロッパの言語は基本的にローマ字読みで日本人にも発音しやすいし聞き取りやすいです。
フランス語はかなり訛っていますね。
今の英語の発音が曖昧で聞き取りにくく、もちろん発音しにくいのはフランス語の影響ではないかと思います。
ただフランス語にもドイツ語にもないth[θ、ð]の音などは古い英語の名残ですね。
ロマンス語 (英語とラテン語の関係)その1~ノルマン・コンクエスト
母語の影響
さて歴史の話はこれくらいにして、どの国のどんな言語を話している人も母語の音の体系ができあがっていて、外国語を学ぶときには邪魔になります。
これは日本人だけの問題ではないので安心してください。
似た音で代用してしまう
たとえば上にも挙げた英語のthの音。
日本にはないので「す、ず」で代用してしまいます。
これまた日本人だけでなくフランス人もおなじです。
すこし安心しましたか。
アメリカのコミックなどで
“Zat eez (ザットイーズ) “というセリフがあったらフランス人だと思ってください。
これは意識して代用しているのではなく、自然に母語のいちばん近い音で発音してしまうんです。
ただ真似してもダメ
今はネットでいくらでもネイティブの発音が聞けます。
それを聞いて真似したつもりでもかならず母語の発音をしています。
毎日、1日10時間、何万回も練習してもネイティブの英語にはなりません。
あなたはまちがった練習をしているのだから。
やってればそのうち自然にうまくなる?
いいえ。けっしてなりません。
なぜならあなたは一所懸命、日本語の発音を練習しているだけだから。
卑近な例では日本人がフラメンコを踊るとかならず盆踊りになってしまうことがあります😄
見様見真似では盆踊りから抜け出せません。
何がちがうのか細部にわたり理論的に解釈して理解しないと盆踊りから抜け出せません。
スキーなんかもそうですね。
いくらうまい人の滑りを見て真似したつもりでも、じっさいにはへっぴり腰のままです。
自己流で何十年滑っても上達することはなくへっぴり腰のままです。
へっぴり腰でも滑れてしまうから。
うまい人の真似を闇雲にしても永遠にうまくなりません。
おじさんがそうでした。
それを変えたのはモノスキーでした。
モノスキーはなんとなく見様見真似では滑れないものだったから。
理屈どおりに体を動かさないとけっして滑れない。
モノスキーの滑りかた。トップページ~これを見ればあなたもモノスキーが滑れる! (スノーボードじゃないの? 「目次」「練習メニュー」)
赤ん坊は耳で聞いて覚える
はいはい。
その通りです。
でもあなたは赤ん坊ではありません。
もう薄汚れてしまっているんです。
日本語色に。
あっ、日本語が汚いということではありませんよ。
赤ん坊はまっさらです。
真っ白です。
何色にでも染められます。
日本人は日本人の遺伝子を持っているから日本語の発音をするのではなく、日本語だけを聞いていたから日本語の発音になっただけのことです。
イギリス人やアメリカ人も然り。
かれらは生まれ持って英語の発音を身につけているわけではなく、オギャーと生まれたその日から、いや生まれる前からお母さんのお腹の中でも英語の発音を聞いて英語色に染まっただけのことです。
外国語。聞いて覚えられるのは、赤ん坊のうちだけ! (舌の位置)
母語体系ができあがった大人はべつのアプローチが必要
完全に日本語色に染まった日本人の脳と口や舌は、そのまま英語を聞いて真似してもけっして英語にはなりません。
音声学 phonetics
そこで必要なのが音声学の知識。
なんかむずかしそう。
いや、なんとか学というとむずかしそうだけど、要するに
おもに舌をつかってどうやって音を出すか
という手引きです。
これを勉強して理解して実践しないかぎり何万回、何十年練習しても外国語の発音は出せません。
口腔断面図
そしてこれを視覚的に理解するのに必要なのが口腔断面図です。
読んで字のごとく口を横から見て舌がどこにあり、どう動くかを表しています。
口の中は見えないので口腔断面図を見ながら舌を動かして、すこしずつ場所を変えていろいろ音を出して自分の耳で確認します。
そしてネイティブの音と比較します。
これは赤ん坊が無意識にやっていることです。
大人は無意識だと自分の母語の音で発音してしまうので、舌を意識して注意深く自分の音を聞きます。
舌がどこにあるかが最重要事項です。
己を知れ
彼を知り己を知れば百戦殆からず (あやうからず)
(孫子の兵法 謀攻より)
英語を攻略するには、まず日本語の音をどうやって出しているかを知る必要があります。
敵の動きをいくら見て研究してもわからないけど、自分にどんな性格があってどんな癖があってどんなふうに動くかを理解すれば、敵とのちがいがわかり敵の性格や癖や動きがわかるようになります。
孫子 (兵法書)
孫子には孫武と孫臏がある。
一般的に孫子の兵法は孫武のものとされている。
孫武:呉孫子
孫臏:斉孫子 (孫臏兵法)
英語が偉いわけじゃない
勘違いしないでほしいのはどっちが偉いとか、どっちが正しいとか、どっちが美しいとかいうことではなく、両者はただ違うということです。
だから、取りも直さず、日本語を学ぶ外国人は自分たちの発音を理解したうえで日本語を練習しないといつまで経ってもバタ臭い訛りの発音から抜け出せません。
英語と日本語のちがい
Japanese phonetic pronunciation 音声学的な発音 ~ 日本語
このリンクの口腔断面図を見ながら読んで、じっさいに舌を動かして音を出して耳で確認してください。
これは1回でできることではありません。
毎日、舌の位置を意識して音を出しているとだんだんイメージできるようになってきます。
赤ん坊は1年ぐらい黙ってひたすら大人の音を聞き、1歳ぐらいになってようやく言葉をしゃべりはじめます。
ああううといういわゆる喃語は自分で音を出して、どうやったらどんな音が出るか確認しているんですね。
もちろん赤ん坊は舌の位置を考えているわけではなく、音を聞いて試行錯誤で位置を変えています。
大人は無意識だと母語の発音になってしまうので、舌の位置が目に見えるぐらいになるまで意識します。
英語と日本語のk, p, tなどの子音はだいたいおなじです。
英語を発音するときに気をつける音を書き出します。
英語 / 日本語です。
r[ɺ, ɹ̠ , ɻ] / ラ行[ɾ]
書いたけどおじさんもこの3つはとても区別できません。
これほど国によってちがう発音のものはありません。
英語と日本語のちがいの絶対王者はこれです。
これは裏を返せば、英語圏の人が日本語を話すときにいちばん問題になる音です。
お互いさまです。
スペイン語は親日的でおなじ弾き音[ɾ]をつかうのでかれらの英語は日本人とおなじようになります。
英語のrは舌をどこにもつけない。
日本語のrは舌を歯茎の後ろに叩きつける。
だから日本語のrはむしろl (エル) に近い音になります。
また英語のrは日本人には「う」に聞こえます。
だって舌の位置が「う」とおなじだから。
何がちがうって英語のrのほうが緊張していて、日本語の「う」はだらしなく力を完全に抜いています。 (後述)
n[n, ŋ] / ん[n, ŋ, ɴ, m, ɲ]
意外と知らないのがこのn (ん) の音。
この音のちがいは小さいのであまり神経質になる必要はありません。
ただ日本人はほっとくと[ɴ]で発音してしまうので、[n]は意識する必要があります。
とくに語末の[n]は「ん」ではなく「ぬ」だと思ってください。
pinは「ぴん」ではなく「ぴぬ」と発音すると英語っぽくなります。
最後の「ぬ」は舌を離さずに歯茎の後ろにつけたままにします。
離してしまうとほんとに「ぴぬ」で英語圏の人にはpinuと聞こえてしまいます。
hang, ink などの[ŋ]は自然にその音になるのであまり気にしなくていいです。
ただ「はんぐ」ではなく「はん (ぐ) 」です。
とくに最後のgは破裂させずに喉の入口に舌根 (文字どおり舌の根っこ) をつけたままにします。
いっぽうinkのkは発音しますが、あくまで[k]であって[ku (く) ]でないことに注意。
kの音
無声破裂音なので声帯を振動させません。
むかしは「インキ (ink) 」「ステッキ (stick) 」そして今でも「ケーキ (cake) 」と書き表していましたが、じつはこのほうが実音に近い音です。
とくに前の母音がiのときは口はそのまま子音のkを発音するので「ク」より「キ」と聞こえます。
bookのときは「ぶく」であって「ぶっき」とはなりません。
近頃はインク、スティック、ケーク (化粧品) などと書くようになりましたが、近い音はインキ、ステッキ、ケーキ (けいき) です。
じっさいには違うんだけど、日本人は無意識に[ɴ]で発音するので舌の位置は[ŋ]とおなじ口の奥、つまり喉の入口なのでだいたいおなじ音になります。
hangerと後ろに母音がつくとgを発音します。
「はんがー」になりますね。
これはいわゆる鼻濁音の「か゜」です。
u[u] / う[ɯ]
これも学校では教えないちがいです。
[u]は口をすぼめて舌を口の奥、喉の入口に持っていきます。日本人には「お」のように聞こえます。
schoolは「すくーる」ではなく「すこーる」に聞こえます。
日本語の「う」はじつは[u]ではなく[ɯ]なんですね。
唇はすぼめません。
ていうか、完全に脱力してだらしない音です😄
舌も力を抜きます。
唇も舌も完全にリラックスして音を出します。
英語の曖昧母音[ə]に近い音です。
だから英語の[u]を発音するときは意識して唇をすぼめて、舌は口の奥に持っていきます。
「お」に聞こえたら成功です。
uは円唇。
「う」は非円唇です。
w[w] / わ[ɰ]
[w]は[u]が子音化したもので唇を緊張させて尖らせます。日本語にゆいいつ残ったワ行の「わ」は「う」とおなじく脱力して軽く唇を近づけるだけです。
だから発音記号も[ɯ]に毛が生えたようなものになっています。
かぎりなくだらしなく脱力していって、ゐ (うぃ) 、ゑ (うぇ) は消えてしまいました。
「を」は文字だけ残り音は完全に「お」と同化しています。
ワ行の「う」はかなり早い時期にア行と同化してしまったので仮名もありません。
おじさんは子どもの頃「を」を[wo]と発音して矯正された記憶があります。
だってワ行じゃん。
賢すぎるのも問題ですね😄
wは円唇。
「わ」は非円唇です。
[ei] / えい (えー) [e:]
日本語では「えい」と書いて「えー」と発音します。
これが正しい日本語です。
例:
英語 えいご→えーご
命令 めいれい→めーれー
でも英語では[ei]は「えい」であって[e: (えー) 」ではありません。
そもそも英語に[e:]という音はありません。


日本語とおなじようにehという音がありますがこれも発音は[e(i)]です。
例:
cake けいく (✕けーく)
make めいく (✕めーく)
race れいす (✕れーす)
日本語の習慣からこれらはみんな「ー」になっているけど英語は「えい」ですよ。
おじさんも無意識だと「えー」と発音してしまうのでかなり意識する必要があります。
逆に言えば英語圏の人は「命令 (めーれー) 」を「めいれい」と発音してしまうけど直してあげましょう。
[ou] / おう (おー) [o:]
これも上とおなじ。
日本語の中で表記と発音が一致しない2大二重母音です。
例:
王様 おうさま→おーさま
狼 おおかみ→おーかみ (「おお」も「おー」と発音します。なぜ「おう」と「おお」があるのかは日本語の記事に書きます)
こちらは上とちがい英語にも[o:]という音があります。
この2つは区別しなければなりません。
例:
boat ぼうと / bought ぼーと
coat こうと / caught こーと
note のうと / naught のーと
code こうど / cord, chord こーど(chordはcordが変化したもので語源はおなじ)
choke ちょうく / chalk ちょーく
日本語では「高校生 (こうこうせい) 」は「こーこーせー」と発音します。
正書法上、おじさんはいずれこのように表記が変わるのではないかと思っています。
というより、こう表記すべきです。
「通る」を「とおる」と書くのか「とうる」と書くのかなどというくだらない問題を出す国語教師はどうかと思います。
もしそんな問題を出すなら、なぜ「とうる」でなく「とおる」と書くのかその根拠を説明すべきです。
おそらくほとんどの先生はその理由はわかっていないでしょう。
もちろんちゃんと理由はありますが、日本語の記事に書きます😄
繰り返しますが発音はどちらも「とーる」なのでおまちがいなく。
f[f], v[v] / ふ[ɸ]
f, v, thは学校でさんざんやっているので言わずもがなです。
「ふ」は完全に脱力して上下の唇の隙間から出す両唇音です。
hi [hi] / ひ[çi]
これはかなり難易度の高いちがいです。
どちらで発音してもコミュニケーションにはなんら問題ないです。
だから学校でも指摘しないですね。
やはり学校の先生も知らないと思います。
ただ、耳のいい人には英語っぽいな、日本語っぽいなというちがいがあるぐらいです。
[f]と[ɸ]のちがいは唇なので目に見えますが、これは口の中の舌の位置なのでわかりにくいです。 [h]は寒いとき手を温めるのに「はあ」と息を出す、あの「は」です。これは舌で出している音ではなく、声帯の隙間を通るすきま風の音です。
それに対して[ç]は、舌と硬口蓋 (口の天井) の隙間を通るすきま風の音です。
ドイツ語にもあります。
これはイ段、hiのときしか出てきません。
イ段はもともと舌が硬口蓋に近づいているので音が口蓋化します。
英語のhiでも舌は硬口蓋に近いので似たような音になります。
厳密に言うとそのすきま風の音が声帯で出ているか、舌と硬口蓋の隙間で出ているかのちがいです。
たとえ声帯のすきま風でも舌は硬口蓋に近いので、そこを通る音も加わります。
意識するなら口の中で音を出さず、喉の奥、声帯で音を出すのです。
感覚としてはhiは喉の奥、çiは口の前の方で出ている音です。
江戸っ子は「ひ」と「し」の区別ができねえ
この2つの音は調音点 (どこで音を出すか) がとても近くて、調音法 (どうやって音を出すか) もおなじなので区別がむずかしいのです。
詳しくはこちらをご覧ください。
th[θ, ð] / す[s], ず[z], づ[dz]
これも学校でさんざんやっているので言わずもがなです。
f, vと同様、舌が口の外に出て目で見えるのでわかりやすいです。
ただ、意識しないと[s][z]になりがちです。
ぢ、づ
諸悪の根源国語分科会により現代仮名遣いでは基本的に「じ」「ず」で書くことになっていて「ぢ」「づ」は邪道として追放されてしまったけど、じつは我々日本人は語頭の「じ」「ず」は「ぢ (dʒi) 」「づ (dzɯ) 」と発音しています。
だから「じつは」はじっさいには「ぢつわ」と発音しています。
気がつかないでしょう😄
いいんです。
母語話者はそれで。
ただ耳のいい外国人はちがう音として認識します。
もしあなたが日本語教師ならこのちがいを知っていなければなりません。
これも音のちがいは大したことではなく、区別がないからとて言葉の意味が変わるわけでもありません。
英語の末尾に現れるdzは[dz]と発音します。
friendsは「ふれんず」ではなく「ふれんづ」です。
もちろん「ふれんず」と発音しても問題なく通じますが、そこが「ん?ちょっと訛ってんな」という部分です。
seseo
スペイン語でもseseo (セセオ) という動きがあります。
スペイン語ではci, ziは[θi]、ce, zeは[θe]なんだけど、それぞれ[si][se]で発音する地域と人々がいます。
その逆もまた然りで、本来[s]の音を[θ]で発音する人もいます。
だからこれらの音を混同するのは日本人だけではないということです。
舌の位置はかなり変わるのですが音としては似ているので起こるべくして起こる現象なのです。
フランス語やドイツ語にはない[θ]の音がスペイン語にはあるのは「ケルト=イベロ族」という共通の祖先のためです。
意外とイギリスとスペインてつながっているんですね。
Cockney (コクニー) はthをfで発音します。
コクニーでなくてBBCのpodcastを聞いていてもBeth (ベス) という人がBeff (ベフ) に聞こえます。
「っ」→「ー」
カタカナ英語では「っ」をよくつかいますが、完全に取ってしまうか「ー」にします。
good グッド→グド、グード
book ブック→ブク、ブーク
foot フット→フト、フート
put プット→プト
set セット→セト
テヌートとスタッカート
日本人が英語を話すときに一つ一つの発音はいいのに全体として日本語っぽくなることがあります。
それは日本語が拍の言語だからです。
日本語では
が・っ・こ・ー・に・い・き・ま・す
のように話します。
これはスピードが速くなってもおなじです。
正確に1拍ずつおなじ速さ、同じ長さでリズムを刻みます。
しかも単に長さが一定なだけでなく、1音1音スタッカート気味に音を切ります。
日本語は「ん」以外はすべて母音で終わるんだけど、その母音を短く切ります。
こんな感じです。
がっ っ こ ー にっ いっ きっ まっ すっ
それから日本語はピッチアクセント (高低アクセント) なので基本的に2つの音程しかありません。
日本語がペチャクチャ聞こえるのはこのためです。
アジアにはペチャクチャ聞こえる言語がほかにもありますね。
英語の母音はつなぎ
それに対して英語はテヌート。
母音はつなぎであって長さが決まっていません。
そして次の子音が出てくるまで音を出しつづけます。
息がつづくかぎり。
それから子音はできるだけ短く、長さを持たないので密着します。
だから
Good morning.
ならこのように発音します。
ぐーーどもーーにん
発音どおりに書くと
Goodmornin.
音程も自由に変化します。
とうぜんアクセントがあるところは強いというより高く、長く発音します。
英語がペラペラと表現されるのは音が滑らかに繋がっているからです。
これを日本人は
ぐっ・どっ・も・ー・に・ん・ぐ
とおなじ長さで1音1音切って、2音程で発音するので日本語にしか聞こえないのです。
あっ、しつこいようだけど英語が偉いわけじゃありません。
そこんとこくれぐれもおまちがいなきよう。
日本語とはそういう言語です。
だから、外国人が日本語を話すときはこれをよ~く理解して、おなじ長さで1音1音切って、2音程で話せばより日本語らしく聞こえるようになりますよ👍️
Japanese beat and pitch accent 日本語の拍と高低アクセント (日本語)
通じればいい
細かいことをたくさん書きましたが、言葉のいちばん大事な役割は相手が言うことがわかり、自分の言うことが相手に伝わることです。
上にあげた発音のちがいは微々たるもので致命的なものではありません。
しいてあげればrだけは気にしましょうか。
あとはべつにいいです。
まず単語を知らなければ発音はネイティブ並みでも、それこそ話になりません。
ネイティブといっても発音はまた千差万別。
日本人が日本語をしゃべっても地域と個人個人でみなちがいますね。
ただあまりにも訛っているとおなじ日本人同士でも理解し合えません😄
だから、開き直らずに発音も練習しましょう。
恥ずかしがらずに堂々とJapanglishを
コミュニケーションを取るにはまず口から音を発しなければ話になりません。
コミュ障など論外です。
言語や発音以前の問題です。
黙っていては何もわかりません。
人は超能力者ではありませんから。
おじさんはもともと耳が悪くて読唇術と読心術を無意識のうちに会得したので、たまに「おじさんて超能力者?」って言われることがありますが。
インド英語やフィリピン英語を持ち出すまでもなく、MotoGPなんかのインタビューを聞いてればわかるけど、イタリア人はイタリア語っぽく、ドイツ人はドイツ語っぽくしゃべります。
イタリア人はイタリア語の発音で、ドイツ人はドイツ語の発音でしゃべっているからです。
日本人は堂々と日本語っぽく大きな声で話しましょう。
でも基本的なところは押さえておかないとまったく伝わらないんでは意味ないですからね。