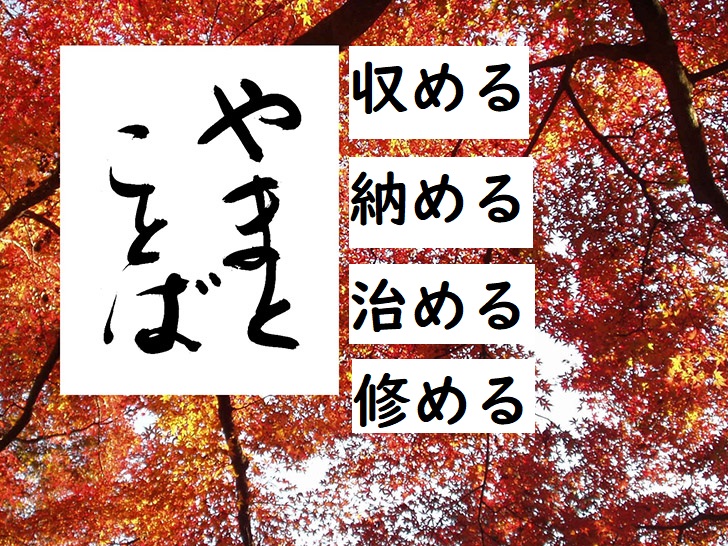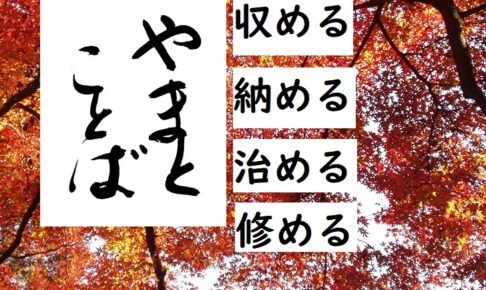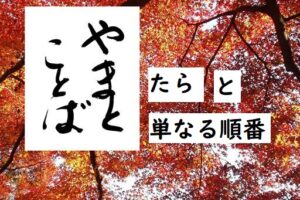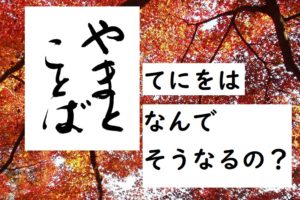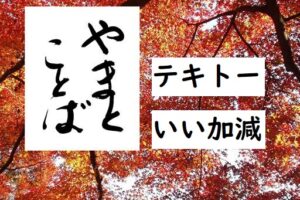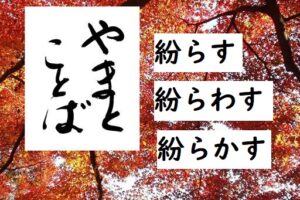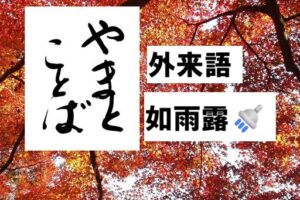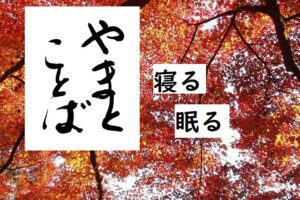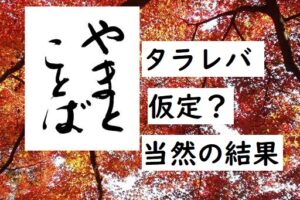目次をご覧になりたい方はクリックしてください→
「漢字」「使い分け」「やまとことば」「1つ」
漢字の使い分け
外国人の学習者にとって漢字は脅威です。
しかし、漢字は日本人にとっても悩みの種です。
たとえば「あう」という漢字は、
合う、会う、逢う、遭う、遇うなどがあります。
「きく」は、
聞く、聴く、訊く。
「おさめる」は、
収める、納める、治める、修める。
学校の先生にとってこれらは格好のテストのネタになります。
やまとことばは1つ
でも、ちょっと待って。
もともとやまとことばでは「あう」「きく」「おさめる」はそれぞれ1つの言葉です。
中国から漢字がはいってきたときにちょっと知ったかぶりの連中が「この漢字はこの意味のときにつかおう」とかってに決めただけです。
漢字輸入の犠牲者たち
「あう」は物と物が面して、あるいはくっつくことです。
人と人が「あう」ときは「会う」で、物と物が「あう」ときは「合う」をつかわなければならない。
「きく」は「耳で音や声を感じる」という意味です。
でも、ふつうに「きく」のは「聞く」で、熱心に「きく」ときは「聴く」で、質問するときは「訊く」と書くことになっています。
「おさめる」は「秩序ある状態にする」という意味です。
漢字では、
収める。しまう。
納める。お金を払う。 (他人のところにしまう)
治める。統治する。
修める。学問を修得する。
ということになっていますが…
さす
差す、指す、刺す、挿す、射す、注す、点す
これらの漢字をすべて使い分けられますか?
できなくていいです。
やまとことばの「さす」は
「細くて尖ったもので一点を示すか、その場所に作用する」という意味です。
その結果、「指を指す」なんてことが起きてしまいます。
苦しまぎれにその場合は「指を差す」を使おうよなんていってますが、そもそもやまとことばは1つです。
労を労う
「ろうを、ねぎらう」といいます。
とてもよくつかいます。
おなじ漢字で「いたわる」とも読ませます。
熟語ではごちゃまぜになる!
使い分けろといいながら、熟語ではごちゃまぜになります。
たとえば、
会合 (かいごう)
人が集まること。寄り合いなどともいいます。
入会/入合 (いりあい)
山や漁場などを共同で利用すること。
その場所を「入会地 (いりあいち) 」といいます。
遭遇 (そうぐう)
とくに好ましくないこと (事故や災難) に「あう」ときにつかいますが、「遭遇」でニコイチです😄
どっちか1つでいいじゃん!
聴聞 (ちょうもん)
「きく」ことです。
使い分けはどうなった?
収納 (しゅうのう)
この言葉はよくつかいますよね。
「物をしまう」ことです。
でも、
収入。懐にはいるお金。
納付。お金を払うこと。 (他人のところにしまう)
のようにおなじお金でもべつの字をつかったりします。
「納める」はお金を払うときにつかうといいながら、収納や納戸 (なんど) など、物をしまう意味でもつかいます。
「納札」「納骨」のようにお金以外でも、他人のところにしまうときにつかいます。
上昇、下降、降下
「のぼる」は「上る」「昇る」どちらが正しいか?なんて愚問ですね。
「下りる」か「降りる」かも同様。
しかも下降と降下がある。
さらに降下の反対語の昇上は存在しないと来てる。
余計な漢字は減らしませんか?
会合や収納のように熟語として定着してしまったものは変えられませんね。
でも、「きく」だったら「聞く」でいいじゃないですか。
「音楽を聞く」
「道を聞く」
でいいじゃないですか?
もっといったら「音楽をきく」でもいい。
言葉と文字は伝える「手段」「道具」
漢字がはいってきたときに「仕分け」をした人は中国語での使いかたを日本語に当てはめたのかもしれません。
ただ、言葉と文字はお互いが意思疎通 (コミュニケーション) するための手段・道具にすぎません。
いかにたくさん漢字をおぼえて使い分けるかが目的になってはいけません。
国語分科会の常用漢字の決めかたも実生活とずれていて間が抜けているところもあるけど、いっぽう漢字検定では誰も見たことがない、一生つかうことがないであろう漢字を出題して受験者はいかにそれをクリアするかというゲームになっています。
中には中国語がよくわからないため、中国での漢字の「元の」「正しい」意味とちがう意味でつかわれているものもあります。
魚偏の漢字はそれが多いですね🐟
鮎 (なまず→あゆ) 、鮑 (塩漬けの魚→あわび) 、鮭 (ふぐ→さけ) 、鮨 (魚の塩辛→すし) 、蛸 (淡水魚の名→たこ) 、鯖 (寄せ鍋、にしん→さば) など他にもたくさんあります。
というかちゃんと日本語に変換されたもののほうが少ないのではないかと思います。
中国人が見たら笑ってしまうでしょう。
まちがった翻訳と使いかたで、「これが正しい」「これはまちがい」と騒いでいるんですから。
参考:旺文社 標準 漢和辞典
ちなみに国語分科会の所属は、
文部科学省文化庁文化審議会国語分科会となります。
長っ😅
先生の立場
わたしは外国人に日本語を教えています。
「収める、納める、治める、修める」の漢字のちがいを説明したり、生徒がこの使い分けを覚えるのに費やす時間と労力をもっとほかのことにつかったほうがいいと思います。
日本人でさえ使い分けできてないのに😅
ただ、立場上「どれでもいいよ」とは言えません💦
生徒がこれで落ちこんだり、日本語を嫌いにならないように、
「もともとの、やまとことばは1つだ」
「日本人も使い分けはできていない」
ということを説明します。
わからなければひらがなで書けばいい。
JLPTなどの試験を受ける人には「試験に受かって資格を取るためには漢字を覚えなければなりません」といいます。
ただそれはあくまで試験のためであって、ほんらいの言語を「修得 (習得!?) 」する目的からは離れていると思います。
日本人のみなさん。
修得と習得のちがいわかりますか?
わからなくていいです✌
習うより慣れろなんていうけど、
習う、慣らう、馴らう、倣う、傚うは、もともとやまとことばでは「ならう」という1つの言葉です。
「なれる」も同様。
だって、「習慣」「慣習」っていう熟語があるじゃないですか。
ちなみにこの2つのちがいわかりますか?
わからなくていいです✌


わたしは日本語教師をしています
プロフィール・レッスン予約はこちら。
表示名はToshiです。
https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese