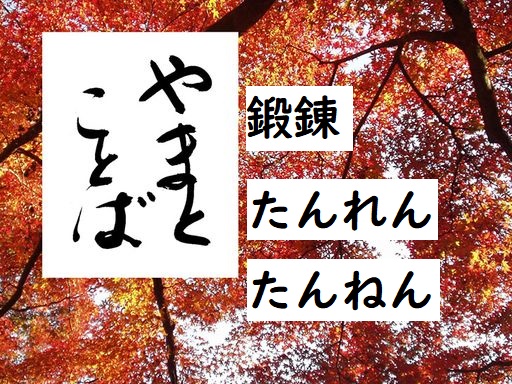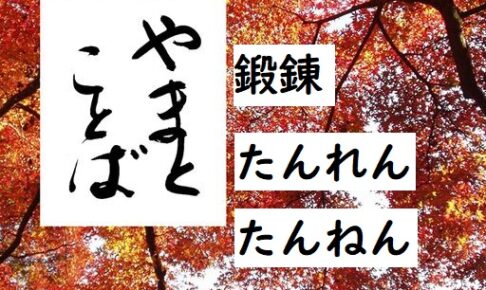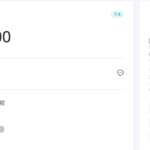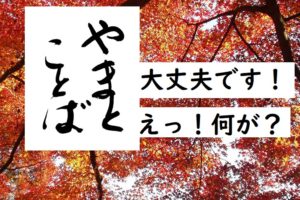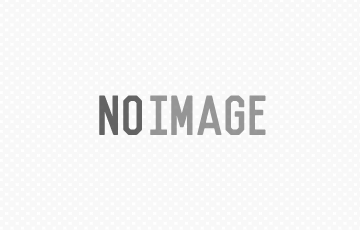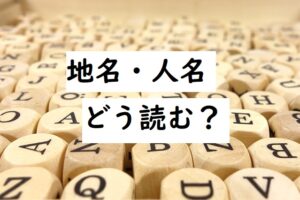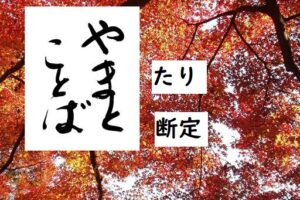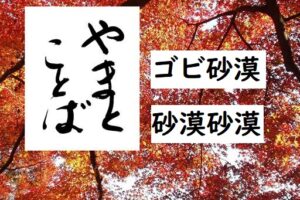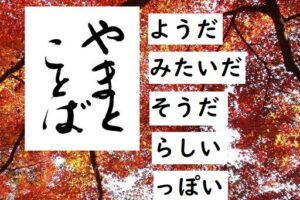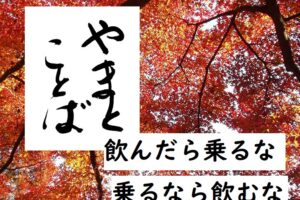目次をご覧になりたい方はクリックしてください→
「ん」「ラ行」「発音」「むずかしい」
鍛錬 (たんれん) → (たんねん)
この記事は自分の舌が口の中でどのように動いているか、発音しながら想像しながら読んでください。
あっ、電車の中では舌の動きだけで声は出さないほうがいいです😄
英語圏の生徒が本を読んでいると「鍛錬 (たんれん) 」を「たんねん」と発音してしまいます。
読みまちがいではなく、その単語が何度出てきても「たんねん」と言ってしまいます。
そこでその単語を繰りかえして読ませるのですが「たんれん」が言えません。
本人も発音がむずかしいと言っていました。
ふつうに「ラ行」を発音するときは気にならないので「ん」の直後の「ラ行」がむずかしいようです。
tanren → tannenになってしまうのには何か理由があると思い考えてみました。
「ん」は日本語唯一の子音にして歯茎音
なんのことかわからないですね😅
日本語の基本は子音+母音
か (ka) 、そ (so) 、み (mi) のように日本語はかならず
「子音+母音」のセットで子音だけで単独に発音することはありません。
かならず母音で終わる
また母音 (あいうえお aiueo) は、子音を伴わないけど、やはり母音で終わります。
母音は舌が離れている
母音の定義は「舌で息をジャマしないで出す音」です。
じっさいには舌の位置や形を変えて音を変化させますが、極端に隙間を狭くして出す「サ行 (s) 」や、歯茎や硬口蓋に舌を当ててから離す「タ行 (t) 」のように息を出す通路をふさぎません。
当然ながら、子音はこの逆で、「舌で息をジャマして出す音」です。
日本語では文字一つひとつ読むたびに母音で終わるのでかならず舌は歯茎や硬口蓋から離れています。
唯一の例外「ん」
「ん (n) 」だけは子音で終わります。
日本語の「ん」にはたくさん発音があるのですが、基本的には歯茎または硬口蓋に舌がついています。
「ラ行」は弾き音
日本語やスペイン語の「ラ行 (r) 」は「弾き音」といって、発音する瞬間に
「舌先を歯茎または硬口蓋に叩きつけて、またすぐ離す」という特殊で高度な音です。
厳密には[ɾ]とrの角が取れた発音記号で表し、英語の[r] (接近音) とは区別します。
歯茎または硬口蓋と書きましたが、人は楽したい生きものなので舌を歯茎まで伸ばさずに、その後ろの硬口蓋あたりにとどめるほうがふつうです。
以後、この記事では硬口蓋とだけ書きます。
英語の「r」は接近音で舌が口蓋などにつくことはなく近づけたまま出すので「ウ~」という唸り声に近いです。
ギリギリ子音だけど、母音と言えないこともない。
「ヤ行 (j) 」は半母音といいますが、「r」もその仲間です。
「ん」→「ラ行」で起こる問題
さてここまで読んでわかった人は天才です。
一を聞いて十を知る、いや万を知る人です👏
ん:舌先を硬口蓋につけたまま
ラ行:発音する瞬間に舌先を硬口蓋に叩きつける
矛盾
困りましたね。
「ん」で舌先はすでに硬口蓋に張りついているのに、つぎの「ラ行」を発音するときは一回、舌を硬口蓋から離してからもう1度叩きつけなければなりません。
前述のとおり、ふつうは母音で終わるので舌は離れているんだけど、「ん」だけは舌先が硬口蓋についた状態でつぎの音を出さなければなりません。
勢いよく離す
そこで苦しまぎれにやっているのが、わざわざ離してもう1度やり直すのではなく、
「硬口蓋に張りついた状態から、あたかも叩きつけたときとおなじように勢いよく離す」
ことです。
いや、ネイティブの日本人ならだれもそんなこと考えてないし、苦しんでもいません😄
ただ、外国語として日本語を学ぶ外国人としては
「ん」+「ラ行」
つまり
「n → r」の接続のときは苦労するんです。
じっさいは日本人はズルしてるんだけど、それがわからず律儀に発音しようとするととてもむずかしい発音の並びになります。
英語ではそもそも「nr」という音の続きが少ないし、あっても英語の「r」は接近音なので「n」と競合しません。
離れるのが遅いと「ナ行」になる
ゆっくり離すと「ん」に引きずられて「ナ行」になってしまいます。
話がむずかしくなるので歯茎音とだけ書きましたが、「ん」は鼻音なので鼻への通路が開いています。
tan-nen
あるいは英語の「l (エル) 」になる
舌が歯茎の後ろについたまま音を出すと英語の「l (エル) 」の音になります。
tan-len
まだこちらのほうが日本語の tan-ren に近いです。
口蓋帆も閉じなければならない
鼻音なので口蓋帆が下がって鼻へ空気が漏れていますが、つぎの「ラ行」を発音するときは口蓋帆を上げて鼻への通路をふさぎます。
これも日本語ネイティブなら知らずにやっているので心配いりません。
舌先を離すのと、口蓋帆を上げるのを瞬時にやらないと、鼻から息が漏れていわゆる「鼻にかかった声 (鼻音) 」になってしまいます。
「n」は本来、歯茎音ですが、つぎに「r」が来るときは無意識のうちに舌先は歯茎より後ろの「硬口蓋」寄りになります。
歯茎の後ろに当てておくと、舌が伸びて素早く離すことができないからです。
ゆっくり離すと「ナ行」の音になってしまいます。
硬口蓋につけておくことで、なかば「破裂ぎみ」に「r」音を出すことができます。
英語の[ṭ]
flapping, tapping 弾音化
英語の letter, party のように母音にはさまれた「t」は舌の動きが速くなると日本語の弾き音「r」とおなじように瞬間的に舌先を硬口蓋に叩きつけるようになります。
これが「レラー」「パーリー」と聞こえるゆえんです。
そして、聞こえるだけでなくじっさいの発音、舌の動きもおなじです。
ただ日本語の「ん」のあとの「ラ行」は「タ行」まで行かない「タ行もどき破裂音」なのでむずかしいですね。
完全に破裂させてしまうと今度は「たんれん」ではなく「たんてん」または「たんでん」になってしまいます。
練習方法
まず「l (エル) 」で発音する
tan-len と発音します。
「l」は舌先を歯茎の後ろにつけたままですが、「ん」のときに舌先をもうすこし後ろの硬口蓋につけておいて、「れ」で勢いよく離します。
「l」が舌先が横に広がっているのに対して、「r」のときはもうすこし舌先を尖らせて硬口蓋に軽くつけます。
「d (ダ行) 」で発音する
tan-den と発音します。
やはり「d」は舌先が歯茎の後ろについているので、上の練習とおなじように、「ん」のときに舌先をもうすこし後ろの硬口蓋につけておいて、「れ」で勢いよく離します。
「d」は「l」とおなじく舌先が横に広がって歯茎の後ろにべったり張りついているので、舌先を尖らせて硬口蓋に軽く触れるていどにして滑らかに、かつ素早く離します。
破裂させると「d」になってしまいます。
また無声音 (声帯を振動させない) だと「t」になってしまいます。
スペイン語では「n」の後ろの「r」は「rr」になる!
スペイン語の「r」は基本的に日本語とおなじ弾き音です。
日本人フレンドリーな言語です😋
語頭の「R」と「rr」はいわゆる巻き舌になります。
巻き舌
「歯茎ふるえ音」といい、歯茎または硬口蓋に舌先を押し当て、息を出すとともに舌を振動させます。
舌は細かく硬口蓋についたり離れたりして振動して「ビビリ音」を出します。
よく英語の先生が英語の「r」を巻き舌といって教えますが「まちがい」です。
英語の「r」は接近音であり、舌をどこにもつけません。
このおかげでおじさんが英語の「r」をきちんと理解したのは50代後半です😅
理解したけどむずかしいです。
nr → nrr
たとえばスペイン語で
honra (体面、面目) という単語は
[ónrra (オンラ) ]と発音します。
「h」は発音しないんだけどスペイン語講座になってしまうのでここでは説明しません。
これは日本語とおなじで、国語学者が決めたわけではなく
「n」で舌が硬口蓋に張りついているので、「r」を出すときに舌が離れて「r 〰」と振動するんです。
スペイン人の場合は、巻き舌になってしまうのが問題になりそうです😅
まあ、巻き舌のほうが「ラ行」であることはわかるので障害はすくないです。
ただ
「にいちゃん、江戸っ子だねえ~」
「てやんでえ~」
てな感じになりそうですが。
日本人にもむずかしかった?
日本語に「ん」はなかった
もともと日本語には「ん」がありませんでした。
「む」か「ぬ」です。
嘘だと思うなら「ん」のつく言葉を思いつくかぎり挙げてみてください。
本、段、県、反…
ついでに「ん」+「ラ行」の言葉も。
鍛錬、関連、混乱、氾濫、近隣、分類…
これらはみな中国から漢字とともにはいってきた「漢語 (中国語) 」とその発音です。
いわゆる「音読み」と呼ばれているものです。
「飛んで」「遊んで」などの撥音便もむかしは「飛びて」「遊びて」といったので近代の話です。
擬声語、擬態語として、ドンドン、ポンポンなどはたくさんありますが、おそらくこれらも、「ドムドム」「ポムポム」のように発音していたのではないかと思います。
名残りとして「ふむふむ」などがありますね。
これらは漢字がはいってきて、ひらがなやカタカナがつくられてはじめて文字として表されるのようになったので昔の人がどのように発音していたかはじっさいにはわかりません。
三位一体
これを「さんみいったい」と読みますが、なんで「三 (さん san) 」+「位 (い i) 」で「さんい (san・i) 」や「さんに (sanni) 」とならずに「さんみ (sammi) 」となったのかを知れば、「三」は「さん (san) 」ではなく「さむ (samu / sam) 」と発音していたことがわかります。
なぜか?
日本語には「ん (n) 」の音がなかったからです。
陰陽師 (おむみょうじ→おんみょうじ) もその仲間です。
日本語の語頭に「ラ行」はなかった
これも「ラ行」ではじまる言葉を挙げてごらん、と言われれば、漢語かヨーロッパのカタカナ言葉です。
しりとりで相手をやっつけるのにつかえるのは、このためです。
だから、日本人も漢語がはいってきてとても「混乱 (こんらん) 」したと思います。


Japanese phonetic pronunciation 音声学的な発音 ~ 日本語
わたしは日本語教師をしています
プロフィール・レッスン予約はこちら。
表示名はToshiです。
https://www.italki.com/teacher/8455009/japanese